皮膚を刺すような太陽の日差し。外に出た瞬間は眩しくて、目も開けられないぐらいの光の強さである。
だが今の彼にとってはそれは些細な問題だった。
「ゼロスくん、早く! 置いてくよ!」
麦わら帽子、白いパーカー、ゆるく上げられたジッパーの隙間からチラリと覗くその下は赤色の水着。水着についている短いパンツを履いているものの白いすらりとした足が素肌のままさらされている。腕には膨らませた浮き輪を持ち、彼女はゼロスに向かって手招きをしている。ホテル前はにぎやかな通りなのだがゼロスにはその声ははっきり聞こえた。
「生きてて良かった……!!!」
ガッツポーズをして悶えるゼロスを止める人間はあいにく誰もいない。何しろ今日今からの行動はゼロスとの二人きりのものだからである。
そもそもどうしてこうなったかというと昨日もロイドたちは海で一日中遊んだのだがだけが体調が優れずビーチのパラソルの下で荷物番になったのが原因だ。しかも途中バテて一緒に荷物番をしていたリーガルによってホテルに運ばれた。
今日ロイドたちは朝から遊園地の方で遊んでいる予定なのだが、は海で遊べなかったことがよほど悔しかったらしい。夜になってもじいっと海の方を見ていたのだ。
それに気づいたゼロスがそっと隣に立ち「俺さまと海にいく?」とにこりと笑えば言い終わる前に「いく!」と即答されていた。普段はゼロスの軽口にからかわれては顔を赤くするなのにこのときは飛びつかんばかりに喜んでいたのだ。実際自分からゼロスの手を取ってぶんぶん振り回して大変嬉しそうに礼を言っていた。
そんなわけで他のメンバーにはかなり心配されつつ二人は今日も一日海で遊ぶこととなった。もちろん、心配されたのはであり、心配の種はゼロスという存在だったが。
「ゼロスくん、早く!」
「はいは~い!」
海というものは人を開放的な気分にさせるものである。普段ならビキニなど着るタイプではないが真っ赤な色のビキニを着ているのだ。昨日は水着すら着れずビーチにいたことがかなり悔しかったというのも手伝っているのかもしれない。
着替えや大きな荷物のほとんどはゼロスが持っている。は浮き輪を持つだけだ。
ひょいひょいとゼロスを置いて先に行ってしまう。
「ったく。楽しげで何よりっと」
シルヴァラントからやってきた少女は生まれも育ちもはっきりしていない。彼女は笑って誤魔化しているのだがシルヴァラントの生まれですらないらしいというのだから驚きである。シルヴァラントの面々はリフィルを除いてあまり気にしていないらいいがテセアラ組とリフィルからすればとんでもない存在である。
特別な力があるわけでも、何かに秀でているわけでもない。笑顔で彼女は時々無邪気に棘を持って人と話す。年頃にしては鋭い棘が、彼女が年齢とそぐわない部分だろうか。
ただ、今の彼女は海を楽しみたい、ゼロスに無邪気に笑いかけるただの少女だった。
海の家に荷物を預け、意気揚々とパーカー片手に持つはますますゼロスの目には眩しかった。普段肌を見せない子の水着姿は反則的である。
旅を続けてきたこともあり体は健康的に引き締まっている。すらり、伸びた手足は昨日さほど日焼けしていないからかまだ白さを見せている。思わず二度見する人間もいくらかいたがその瞬間ゼロスはサッと自分が羽織っていた大きめの上着を上からかぶせた。
「わっ! なに!?」
「んー、虫よけ」
「蚊でもいた?」
「まあそんなとこ~。んじゃ、いきましょうかレディ?」
羽織らせたパーカーを恭しく取り去り膝を突いて手をさしのべればゼロスの予想通りは顔を真っ赤にして口なんて金魚みたいにパクパクしたものだからゼロスはくすくす笑いだして、立ち上がるなりそのまま手を握って浜辺へと歩きだした。
あたふたと手に力を入れて、やがてされるがままになる少女にゼロスはけたけたと笑ってみせた。
ぷかりぷかり。足の着かない沖まで出て泳ぐとなんとなく不安なのかは浮き輪にしっかりと捕まっている。ゼロスははぐれたら困るとかいろいろと名目をつけて同じように外側から彼女の浮き輪に捕まってた。
「海きもちーねえ」
「俺さまはちゃんとこんな至近距離でも怒られないことのがしあわせだけどねえ」
「……ゼロスくん」
軽口を叩けばため息交じりにゼロスの名を呼ぶ。最初の頃はゼロスの言葉に慣れないのか頬を赤らめることもあったが最近では他の女性陣と同じようにゼロスの軽口を流したり適当に返事をするようなっている。
ただ元々律儀な性格なのか軽口も流さずにいちいちちゃんと呆れてくれることが多い。今も呆れた顔をしていた。ちなみに他の女性陣の場合は鼻で笑うか何もなかったかのように扱うのでまだ可愛い反応である。
そんな彼女は浮き輪を持つ手を少しだけきゅっと力を込めたかと思えば片手をそっと浮き輪から外してゼロスの手をとんとんと指でつついた。
「ねえゼロスくん」
「んー?」
「この水着、ゼロスくんに見せたくて着たんだ」
くりっとした瞳がゼロスの瞳の中に入り込んできた。ゼロスが、彼女を見つめていた。いつもと同じ光。けれどいつもと違うまなざし。
何を言おうか、いつものような軽口を口にしようとすれば何も出てこない。ただ阿呆のように目を真ん丸して、口をを開いて閉じて。やっと出てきた音は間抜けそのものだった。
「は、」
「……ってゼロスくん単純だなあ。自分がやることやり返されたらビックリしてる!」
もうそのときのはいつもと変わらない。いつもよりは茶目っ気たっぷりの、愛嬌ある笑顔をゼロスに見せていた。太陽よりもきらきら。ゼロスの視界を占めている。
そこまでの情報が脳内に行きわたるとゼロスもいつものようににやりと笑う。いつも通りのゼロスだ。
「ちゃんも、結構俺さまに慣れてきたわけか」
「そうだなあ、ゼロスくんが実はかわいいってのは、わかったかもねえ」
ふふふん。鼻歌でも歌いそうなぐらい上機嫌で、は先ほど話した手を持ち上げぽんぽんとゼロスの頭を撫でた。軽く、髪に触れるだけの感覚。ぽたり。腕から滴が伝って頭に落ちた。
やられた。
小さくつぶやいて顔をしかめたゼロスにはにこにこと笑うだけだ。
「……実は小悪魔?」
「うーん、実はいじめっこ、かも?」
あれ、俺さまの知るあのほわほわと初心な反応を見せるちゃんはどこにいったの。
そう言いたげにぽかんと呆けた顔をするゼロスがよほどおかしかったのだろう。けらけら。かわいいかわいと笑う。
もちろんかわいと言われ大人しくするゼロスではない。ムッとして、けれどすぐにその表情を押し隠してひょいと、浮き輪を隔てたの耳元に近づいていた。
「そんなにかわいことされちゃうと、俺さま本気になっちゃうよ?」
ふっと音と一緒に吐息も残して、もしかしたら唇が触れたかもしれない。そんなゼロスの行動にの体は大きく震えたかと思えば。
「あ」
「え」
力が抜けたのかそのまま浮き輪からスルリとぬけ落ちた。
「ちゃん!?」
ゼロスは慌てて片腕で浮き輪を抱え、もう片方の腕での体を抱き寄せるとホッと一息ついた。抱き寄せられたの方も予想外だったらしく目を丸くしてゼロスを見ていた。
腕の中にある存在にゼロスは全身に入った力をほんの少し抜いてふっと微笑んだ。も強張ってはいたが笑顔を見せる。
「力抜けた」
「そんなに良かった?」
「ゼロスくん!」
叩いてやりたいだが力の抜けた体を支えているのはゼロスである。どうしようもなくてただ斜め上の相手をにらむしか出来ない。
完全に密着した状態なのだが浮き輪も自身も支えてもらっているので足が着くところまでは下手なことはできない。
「ゼロスくん、浮き輪被せてよ」
「せっかくだからこのまま浜まで戻ろうか~」
「私が悪かったから嘘嘘許してさっきのなんかいっぱいいっぱいでしたごめんなさいだから無理ほんと無理だから浮き輪返して~!」
泣きつくにゼロスはうーん、と困ったような顔をして、浮き輪を渡そうとしない。
先ほどまでの小悪魔振りはどこにいったのか今や顔を真っ赤にして涙目になっている。
そこまでくるとさすがのゼロスも苦笑混じりで浮き輪を返してやる。そこでようやくもホッとしたらしくいつものような笑みを浮かべた。
「あんまり、泳ぎ得意じゃないの」
「なるほどね。けどさっきまでの小悪魔は一体何だったのかな~? 俺さまもさすがにビックリしたんだけどな、あれ」
斜め向こうに視線をやり顔を見せようとしないの耳はほんのりと赤かった。
にこにこ。思わず浮かべた意地の悪いゼロスのその笑みは誰にも見られていない。浮き輪が隔てる中でそっと、先ほどのように乗り出そうとすれば浮き輪の動きで気づいたのか慌てて口を割った。
「リーガルさんと、リフィルさんと、話してたの」
「はい?」
「昨日、二人がお酒飲んでて、私も混ざって飲んでたんだけど、そのときに、」
ああ、そういえばこのからかいがいのある彼女は意外と酒がいける口だった。見た目の割に飲める年だし、弱くもない。ゼロスはあまり酒の席に混じらないがよく三人が酒を飲んでいることは知っていた。
しかしなぜどうして三人で酒を飲んでいる席で今日の小悪魔の話になるのか、ゼロスもさすがにわからなかった。
「で、なんで小悪魔になったのか、俺さまにも説明してくんないの?」
大概の女の子ならこの笑みで一発KOである。頬を染めて、もしくはここまでくるまえにゼロスになぜかを話してくれる。
しかし目の前の少女はゼロスと一緒に旅をしている少女である。流してボケて呆れる女性たちと一緒におり、ゼロスの軽口に乗せられても瞳をハートにするわけではない。
当然、ここでの悩殺スマイルにも彼女は屈しなかった。
「乙女のひみつ」
乙女の中にリーガルははいるのか。
そっちにツッコみを入れてしまったせいで結局小悪魔の原因ははぐらかされてしまいその日は終わってしまった。
海水浴も終え、着替えた二人は砂浜を歩きながらホテルへと戻っていた。
そっと気配を消すように少し立ち止まり、はゼロスの背を見つめる。今だけは振り返らないように、聞こえませんようにとはその背中にそっと先ほどの答えを向けた。
「ゼロスくんと、二人きりだったからだよ」
どうしたら軽口ばかりのゼロスと一日過ごせるか、どうしたら恥ずかしがってばかりでなくて済むのか。真剣に頭を悩ませていたに対して返ってきたリフィルとリーガルの返事は、「少しぐらい慌てさせてみたら」だった。酒の席のこととは言えはそれを覚えており、自分を役者と思い込むぐらいの気持ちで今日に臨んだ。
その結果があの反応であり、の精一杯だったのだった。あのあとはいつものように軽口を叩かれ遊んで、おしまい。
「ゼロスくんのばーか」
気付いて。やっぱり気づかないで。
の小さな言葉は海のさざ波に消えていく。
「ちゃん?」
「今いく!」
走り出したの後ろには、二人分の足跡がたくさんの足跡と一緒に残されている。
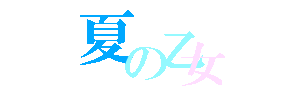
夏の乙女