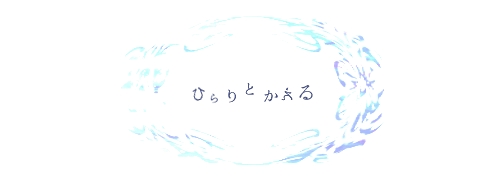曲線。
ゆるりと続く線は丸みを帯びていて、それは彼にとって別ものだった。少なくとも、己にも同じ呼ばれ方をする部位が体の中にあるというのに、彼の目に彼女のそれは同じものには見えなかった。少なくとも、その日その時その瞬間は。
果たしてそれが本当にそうだったかといえば、次の日の彼は首を傾げるだろう。本当にそうだったのだろうかと己の感覚を疑うだろう。そもそも、同じ部位を持つのに極端に彼女のそれだけが丸みを帯びているわけではない。強いて言うならばそれは彼女が女で彼が男だから発生する性差からの丸みだ。彼の感受性が彼女の丸みをその時強く感じた、ただそれだけの話だった。
それなのにどうしてか、彼は彼女のその、誰もが持っているし大して差のないであろうそれが目に入って仕方がない。
「あの」
「何?」
見られていたことに気が付いていないのか、彼女は声をかけられて初めてその視線を上げた。黒い瞳がぱちり。彼の瞳と見つめ合う。ぴたりとはまるパズルのピースのように馴染んでいく感覚を、彼は表に出さず味わいながら数秒、ただその瞳だけに意識を注いだ。
期末テストが近いからと、部活が終わった彼と塾帰りの彼女は近くのファーストフードに入って勉強をしていた。
彼氏と彼女かと言われれば、お互いにいいえと、否定するだろう。部活帰りと塾帰りに時間が合えば時折一緒に勉強をしたり、好きな本のおすすめをしあったりしても、それは付き合っていることだとは言えなかった。彼にとって付き合うということは相手に了承を得て初めて名づけられる関係性である。彼女も恐らくそうだろう、と彼は踏んでいる。
だから、今日のこれは勉強会で、いつもよりはテストという目前の課題ゆえに言葉少なにペンだけが動いているという、さして特別なことはない日常の範囲内の一日のはずだった。
雑然とした店内も、空になりかけたシェイクの容器も、二人で会う時間帯も、何もかも、不自然なところはない。他にも友人や恋人と、あるいは一人で店内での時間を過ごす人は多くいる。彼らのようにテスト前だからとテーブル席を確保して長居を決める学生も少なくない。
なんてことのない一日で、向かい側の彼女だけが何のきっかけもなく、不意に彼の世界で変化した。先ほどまで、そうと感じるまでとあとで、彼にとっての彼女はもはや別の生き物に近かった。
「手、小さいですね」
「? 黒子に比べれば、小さいと思う」
脈絡のない言葉に彼女は眉をしかめて感想を述べる。その眉のしかめ方が少し苛立ったように見えて、苛立っているわけではないとわかっている彼にとっても、少し不安を感じさせた。もったいないと、以前言えばそんなこと言われたことなかったと、初めて知ったらしい自分の挙動に彼女はまた眉をしかめていた。多分、困惑していたのだろう。
ペンを握っていない手をひらりと返し、ついと彼の手に視線を走らせる。比べるだけの何の熱もない動作だ。
「確かに、そうですね」
その手の動きにさりげなさを装って、手のひらを彼女の手の前に出せばつられて彼女はその手を彼に合わせた。ぴたり。合わせられた手はどこからどう見ても彼女の手よりも彼の手の方が大きかった。比べるまでもなく。
それでも実際に比べてみれば思っていた以上に彼女の手は黒子の手よりも小さくやわらかかった。
「ほら、ね」
そうしてひょいと手を離してまた彼女の視線は下へと落ちる。国語の教科書。古文のページ。書き写した本文を品詞分解している。
手のひらは下へ。彼の視線はちらりと彼女のそのやわらかな手へ。
単語の隣に字を綴っていくその手をいつまでも追い続けたくなるのを振り切って、彼もまた教科書へと視線を落とす。数学。今日授業で聞いた公式を、彼は必死に思い出す。
もうそろそろ、と言われれば彼もええ、と時計を見て、それから勉強道具を鞄にしまう。
二人で勉強をするのは短くて一時間。長くても二時間。かわした言葉はほとんどない。時折わからないところを聞くぐらい。今日は、手と手を合わせてみたけれど。
あのいつもと違うやり取りと彼の変化を除けば世界は彼にとっていつもと変わらない。時間が迫れば二人は片づけを始めるし、それぞれの家へと帰っていく。
じゃあまた明日と、何もなかったかのように別れを告げ、彼は歩き出す。
ただ不意に振り返った時、彼は見つけてしまった。
雑踏の中、彼女が立ち止まり、その手のひらをじっと見つめているその背中を。
あ、と思ったときには彼女は人影に消え、再び捉えたときはもうまっすぐ歩き出した後だった。
「……」
手をくるりと反転させ、さほど大きいと思わぬ己の手のひらを見つめて、彼はふらふらと歩き出した。